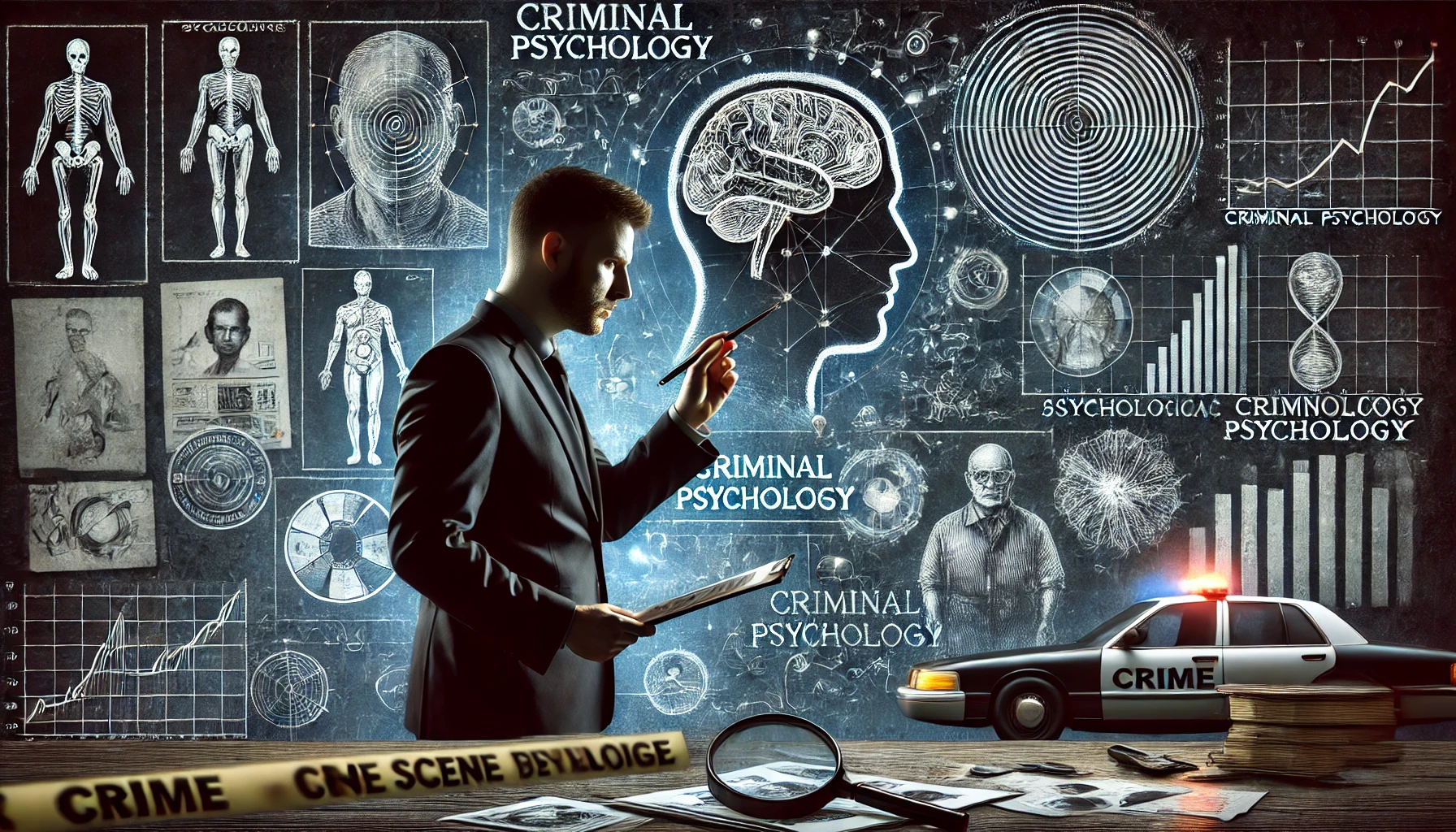犯罪心理学は、なぜ人は犯罪を犯すのか、その心理的要因を探る学問です。生まれつき犯罪者になりやすい性格はあるのか?環境が人を犯罪に走らせるのか?犯罪者と一般人の脳の違いは?こうした疑問に、科学的なデータと実験を用いて迫ります。
本記事では、犯罪心理学の面白い研究や実験、実際の犯罪傾向について紹介し、「犯罪は本当に防げるのか?」というテーマを深掘りしていきます。
1. 犯罪者の脳はどう違うのか?
脳科学が明らかにした犯罪者の脳の特徴
近年の脳科学研究では、犯罪者の脳は一般人と異なる構造を持つことが示されています。特に、前頭前野(感情のコントロールや判断力を司る部位)が萎縮しているケースが多いと報告されています。
- 殺人犯の前頭前野の活動が正常者より約15%低下【Raine et al., 1994】。
- 前頭前野が未発達な人ほど衝動的な行動をとる傾向が強い。
サイコパスの脳の違い
サイコパス(反社会性パーソナリティ障害)の脳を調べた研究によると、扁桃体(感情を処理する脳の部位)が平均より18%小さいことがわかっています【Gao et al., 2010】。これは、サイコパスが他人の痛みや恐怖に鈍感である理由の一つと考えられています。
2. 遺伝 vs. 環境:犯罪者は生まれつき決まるのか?
犯罪遺伝子(MAOA遺伝子)
一部の研究では、特定の遺伝子が暴力的行動と関連していることが示唆されています。その代表例が「戦士遺伝子(MAOA-L)」と呼ばれるものです。
- MAOA-Lを持つ人は攻撃性が高く、暴力犯罪を犯す確率が1.5倍高い【Caspi et al., 2002】。
- ただし、全てのMAOA-L保持者が犯罪を犯すわけではなく、環境要因と組み合わさることで影響が強くなる。
環境が犯罪に与える影響
犯罪率が高い地域では、以下の環境要因が共通して見られます。
- 家庭内暴力を経験した子供は、成長後に暴力的行動をとる確率が約4倍【Widom & Maxfield, 2001】。
- 貧困層の子供は、犯罪を犯す確率が2.5倍【Sampson et al., 1997】。
つまり、遺伝だけでなく、環境も犯罪の要因として大きな役割を果たしているのです。
3. 嘘発見器は本当に機能するのか?
ポリグラフ検査の信頼性
ポリグラフ(いわゆる嘘発見器)は、心拍数・呼吸・発汗量などの生理反応を測定し、嘘をついたときのストレス反応を検出する装置です。しかし、科学的な検証では「正確に嘘を見抜ける確率は約60〜70%」とされ、信頼性に疑問が投げかけられています【National Research Council, 2003】。
脳波(EEG)を使った嘘発見技術
近年では、脳波(EEG)を使った嘘発見技術が開発されており、精度は約80%以上に向上していると言われています【Farwell & Smith, 2001】。
4. 「犯罪の予測」は可能なのか?AIの活用
AIによる犯罪予測システム
最新の研究では、AIを活用した犯罪予測システムが導入され始めています。
- 顔の表情や行動パターンを解析し、犯罪を犯す可能性がある人物を特定。
- 犯罪発生率が高いエリアをAIが予測し、警察の巡回を最適化。
アメリカ・シカゴ警察が試験導入したAI犯罪予測システムでは、犯罪発生率を約15%低減することに成功しました【Chohlas-Wood et al., 2020】。
5. 未解決事件と犯罪心理学
「プロファイリング」はどこまで有効か?
FBIなどが行う「犯罪プロファイリング」は、過去のデータをもとに犯人の特徴を分析し、捜査を進める手法です。しかし、科学的にどこまで有効かは議論があります。
- 成功率は60〜80%とされるが、経験則に依存する部分も多い【Alison et al., 2010】。
- シリアルキラーの行動パターンを分析し、次の犯行を予測する試みも進行中。
結論:犯罪心理学は「人間の本質」に迫る学問
犯罪心理学の研究は、単に「犯罪者を捕まえる」ためだけでなく、「なぜ人は犯罪を犯すのか?」「どうすれば犯罪を減らせるのか?」という根本的な問題を解明するための学問です。
- 脳の違い、遺伝と環境の影響、AIによる犯罪予測、嘘発見技術の進化など、科学の進歩とともに新たな知見が次々と明らかになっています。
- 今後、犯罪心理学がさらに発展することで、より安全な社会を築くヒントが見つかるかもしれません。